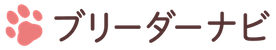愛犬をケガや病気から守るために健康管理は必須
大切な愛犬にいつまでも元気でいてもらうためには、ケガや病気の予防が欠かせません。そのためには、何といっても日々の健康管理が必要です。
では、ワンちゃんの健康を守るためには何をするべきなのでしょうか?
今回は、健康管理の考え方から方法、アプリの紹介など、ワンちゃんの健康に関する情報をご紹介していきます。
愛犬の健康管理用チェックシート
ワンちゃんの健康管理といっても、具体的に何をすればいいのか分かりませんよね?
どんな状態が正常で、どうなると傷病の可能性があるのか。それが分からなければ病院に連れて行くべきかどうかすら分かりません。
ここでは、ワンちゃんのどんな部位にどんな症状が現れたら注意すべきなのか、各10個程度の項目を、チェックシート形式でご紹介します。
目や耳に異常はない?身体のチェックシート
・目
涙目や充血、濁りなどが見られるようなら、何かしらの異常が起きているかもしれません。
特に、パグやシーズーを代表とする短頭種は、目の傷や病気に気を付ける必要があります。チワワやプードルなど、涙やけが多い犬種は、目を傷つけないよう注意して目の周りをお手入れしてましょう。
また、良くものにぶつかるなど、おかしな行動が増えたら目が見えていないかもしれません。場合によっては、脳や体など他の部位に原因がある可能性があります。
<チェック>
□目ヤニが多い
□涙が多い
□充血している
□痒がってしきりに顔をこする
□目が左右異なる(色、瞳、色など)
□瞳が濁っている
□動くものを目で追いかけない
□目の近くを触ろうとすると避ける
□瞬きが異常に多い
□眼球が突出している
・耳
耳の病気を予防するには、洗浄液を使った定期的なお手入れが大切です。
犬の耳は人間の耳と比べて入口から比較的浅い所に鼓膜があるため、お手入れの際は注意しましょう。特に垂れ耳の犬種や耳周辺に毛が多い犬種は、湿気が溜まりやすいため、定期的な耳のお手入れを心掛けてください。
慣れないうちは、獣医さんやトリマーさんに相談するのもおすすめです。
<チェック>
□耳垢が多い
□耳垢がべたつく
□耳を気にする、痒がる
□しきりに頭を振る
□臭いが気になる
□音への反応が鈍い
□耳から出血がある
□常に首を傾けている
□色の着いた耳垢が出る
・鼻
「犬は鼻が濡れていれば健康」といわれることもあるように、鼻の状態はワンちゃんの体調を表す一つのバロメーターといえます。健康な鼻は、乾燥が少なく、鼻水や鼻血などがない状態です。ただし、「一概にこういう鼻の状態が悪い」というものではないので、「いつもと違う状態=不調を抱えている」と考えておくといいでしょう。
特に、短頭種は鼻の異常が起こりやすい犬種なので注意が必要です。
<チェック>
□鼻が乾燥している
□鼻水が多い
□鼻血が出ている
□大きないびきをかく
□くしゃみが多い
□呼吸しづらくしている
□鼻が変形している
□鼻水に色と粘り気がある
□呼吸が荒い
・口
ワンちゃんのお口のケアで、何といっても毎日の歯磨きがオススメです。しつけの中でも歯磨きは比較的ハードルが高いので、幼い頃から慣らして嫌がらずに歯磨きできるようにしましょう。
口腔内の異常は、歯肉炎など口腔内のトラブルだけでなく、感染症や脳神経の病気が原因の場合もあります。歯石がないのに、口から異臭がする場合は、肝臓や腎臓といった内蔵に異常があるかもしれません。
口臭が少なく、歯は歯石のない白色で、歯茎はピンクか黒色の状態が理想なのです。
<チェック>
□口臭がきつい
□よだれが大量に出る
□よだれに血が混じっている
□口腔がただれている
□歯茎が赤い、または白っぽい
□口腔内に出血がある
□しきりに口の周りを気にする
□粘膜の色がおかしい
□食べ物を飲み込めない
□顎、口元がけいれんしている
・皮膚、被毛
犬種によるものの、健康な皮膚の状態は一般的に白色やピンク、黒色で、被毛は毛づやが良くふさふさしていることが望ましいとされています。
皮膚や被毛に異常が起きる原因の多くは、ノミやダニなどの外部寄生虫の感染です。その他、アレルギーや打撲などのケガ、ホルモン異常の可能性もあります。
かゆみを伴う皮膚病の場合、爪を立てて掻くことで傷つき悪化する場合があるので、こまめにブラッシングをして、異常がないかチェックするようにしましょう。
特に長毛種は皮膚の異常を見つけにくいため、意識して確認するようにしてください。
<チェック>
□湿疹がある
□腫れやしこりがある
□痒がる
□フケが多い
□臭いがする
□集中的に毛が抜ける
□皮膚の色に異常がある
□被毛がベトつく
□被毛が乾燥してパサつく
食欲は?排便は?日常行動のチェックシート
・食欲や水を飲む量
ワンちゃんの飲食の有無は、直接健康に結びつく問題です。
いつもの食事量・飲水量を把握して、過度の増減がないか確認するようにしましょう。さらに体重も調べておくことをおすすめします。ワンちゃんの性格によっては、ストレスで食欲が減退する場合もあるので、その点も考慮しておくといいでしょう。
鼻を近づけるなど食べたそうな仕種を見せるのに食べない場合は、喉や口の中、鼻、脳などに障害があるかもしれません。
<チェック>
□食事の量が減ってきた、まったく食べない
□食べたそうなのに食べない
□食事の量が多すぎる
□急激な体重の増減があった
□飲水量が減った、まったく飲まない
□飲水量が増えた
□水を飲むときに大量のよだれが出る
□食事を吐き戻す
□食欲がなく不調が見られる
・呼吸
息が荒い、舌や唇の色がおかしい、呼吸音に異常があるといった症状が確認できる場合は、十分に酸素が取り込めておらず上手く呼吸ができていない可能性があります。呼吸は生命に関わることなので、異常が確認できたらすぐに動物病院に連れて行きましょう。
呼吸器系の問題以外にも心不全の症状の1つとして咳をすることがあり、何かしらの重大な疾患が原因の可能性があります。
特に短頭種は呼吸の問題を起こしやすい犬種ですので、よく観察するようにしてください。
<チェック>
□呼吸が普段より速い、または遅い
□ヒューヒュー、ゼーゼーといった呼吸音がする
□口で呼吸している
□胸が大きく動いている、など
□体を冷やしても呼吸が収まらない
□原因不明で呼吸が荒い
・排泄
人間の赤ちゃんと同じように、ワンちゃんも排泄物のチェックが健康状態の確認になります。食事とともに重要な健康のバロメーターです。
単純な下痢や便秘、多尿などの不調であれば一過性のものかもしれませんが、急性であったり長く続くようなら、何かしらの病気を患っている可能性があります。
特に注意すべきは、長期間排泄がない場合。一説には、ワンちゃんは3日間排尿がないと尿毒症で死にいたることもあるとのことなので、気付いたらすぐ獣医さんに見てもらいましょう。
<チェック>
□ ウンチの色、状態(硬さ)、におい、回数
□ 尿量、色、不純物、におい、回数
□血便が出た
□便に虫がいた
□激しい下痢をした
□トイレに行くが尿の量が少ない
□排便時に声を出す
□尿の色がおかしい
□数日排泄していない
□下痢をして痩せてきた
・睡眠
人間と比べてワンちゃんの睡眠時間は長く、年代によって以下のような睡眠時間が必要といわれています。
子犬:18~19時間/日 眠りが深い
成犬:12~15時間/日 大型犬の方が長い傾向
老犬:18~19時間/日 疲労回復に時間がかかる
もちろん個体差はあるものの、「あまりにも長時間寝ている」「全然寝ない」、といった様子を見せるようなら、過度のストレスを抱えているか何かしらの病気を患っている可能性があります。
<チェック>
□ 睡眠時間が過剰に長い、もしくは短い
□ 寝てもすぐ起きてしまう
□ 寒くないのに丸まって動かない
□急にイビキをかくようになった
・行動
普段の行動と余りにも違う行動をしたり、逆に全く動こうとなくなったりしたら注意が必要です。また、ケイレンなど、見た目に異常と分かるようなら、生命の危険があるかもしれないので、早急に動物病院へ連れて行きましょう。
ワンちゃんの異常に一早く気付けるのは、普段から一緒に生活している飼い主のあなたです。日頃から愛犬の様子をつぶさに観察してどんな動きをするのか憶えておきましょう。
<チェック>
□活動時間が短くなった
□散歩に行きたがらなくなった
□段差を嫌がるようになった
□遊びたがらなくなった
□異常に活発になった
□興奮して落ち着きがない
□目的もなくただ動き回る
□反応や動作が鈍い
□歩くとよろけたりする
□意識がない
□常に頭が傾いている
□足をかばいながら歩く
□壁や家具に良くぶつかる
□眼球が震えている
手元で簡単!ワンちゃんの健康管理用アプリ
スマートフォンの普及で、様々な管理や調べ物が簡単に、アプリ一つでできるようになりました。それは、ワンちゃんに関することも例に漏れず、様々なアプリが提供されています。
ここでは、ワンちゃんの飼い主さんにおすすめしたいアプリをご紹介します!
ワンちゃんの生活にぜひ、お役立てください。
体調管理アプリ「ハロペログ」
大切な家族である、ペットのための体調管理アプリです。
過去の履歴含め、動物病院で診察された処方箋・診察料などのデータを、スマホから一目で確認することができます。
ワンちゃんに欠かせないフィラリアの予防日、予定日の自動登録や日々の体重変化をグラフで簡単に管理することが可能。
いざという時のための、ペットの応急処置ガイドもあります。
参考 ペットのための体調管理アプリハロペログ
愛犬との生活に役立つ「ペット手帳」
「ペット手帳」は動物病院様と飼い主さんをつなぐスマートフォンサービスです。
専門家が監修した成長や季節に合わせたコラムを毎週お届けするほか、お手入れやしつけの方法を動画で紹介。動物病院でよくある質問に獣医さんや専門家が回答するなど、簡単に使える充実した機能が魅力のアプリです。
愛犬の健康管理に役立つ毎日の記録を残す機能も充実しています。
参考 あなたとペットに安心の毎日をペット手帳
専門家がアドバイスしてくれる「いぬノート」
「散歩時に言うことを聞いてくれない…」「吠えて中々鳴きやまない…」
そんな様々なお悩みを抱えた飼い主さんを、多くの実績を積んだトレーナー・獣医がサポートしてくれるのが「いぬノート」です。
しつけや病気の悩み、犬友との交流など、ワンちゃんの飼い主さんに嬉しい機能が充実しています。
参考 プロのドッグトレーナーが愛犬のしつけ問題を解決いぬノート
定期的な健康診断で重大な傷病にも早期対応!
大切な家族であるワンちゃんに、健康で長生きしてもらうためには、日々の健康管理は欠かせません。飼い主さん個人ができることも決して少なくはありませんが、それ以上に定期的な健康診断は重要です。
しかし、定期的な健康診断といっても、どの程度の頻度で受ければいいのでしょうか?
健康診断はどのくらいの頻度で受ければいいの?
最も身近な人間である飼い主が普段からチェックすることで、ケガや病気を早期に見つけることができますが、それだけでは十分といえません。やはり、動物の病気に関する専門家である獣医さんに定期的な健康診断をお願いしたいところです。
もちろん、体調の悪さが確認できる時はすぐに診察を受けさせるべきですが、健康診断を受けることで、日常生活では気付けないちょっとした異変を発見することができるでしょう。
理想的な健康診断の頻度は、ワンちゃんの年齢によって異なります。
下記に、年齢ごとに受けさせたい健康診断の頻度をご紹介しています。
1~6歳:年1回
7~10歳:年2回
11歳~:年3~4回
ただし、これはあくまでも目安にすぎません。
多くの獣医さんが「年に1度でも健康診断は受けたほうがよい」というように、定期的な健康診断は、ワンちゃんの健康を維持するためにも行っておくことをおすすめします。
まとめ
言葉で自分の状態を説明できないワンちゃんの健康を守るには、何よりも飼い主の気遣いがなくてはなりません。
日々の健康チェックから定期的な健康診断まで、愛犬にいつまでもを元気でいてもらうために、できることは全てやっておきたいところですね。
ワンちゃんを迎えるなら、ワンちゃんを迎える前も迎えた後も、丁寧にサポートしてくれるブリーダーからワンちゃんを迎えることをおすすめします。ブリーダーから子犬を迎えれば、犬舎での生活など詳しく丁寧にアドバイスをもらうことができるでしょう。
ブリーダーナビは、安心価格と取引保証で、顧客満足度98.9%!掲載されているワンちゃんの頭数も日本最大級の子犬販売サイトです。ブリーダーナビを、ぜひ一度ご覧ください。
著者/ブリーダーナビ編集部