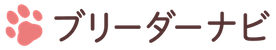何事にも初めてはあるものの、ワンちゃんを家族に迎えるというのは、日常において大きなイベントの1つといえるでしょう。「迎える方法は…」「どんな準備をすれば…」など、多くの疑問があって、何から手を付ければいいのか分からないという人も少なくないと思います。
今回は、そうした不安を少しでも解消してもらえるよう、柴犬の子犬を迎えるにあたって必要な準備や心構えなどをご紹介します。
また、「柴犬を飼ってみたいけど、飼えるのか不安…」という方は、「柴犬の飼い方」についてまとめた下記のページもぜひご覧ください。
 初心者向け柴犬の飼い方
初心者向け柴犬の飼い方
選択肢は「ペットショップ」「ブリーダー」「里親」の3つ
ワンちゃんを迎える手段は「ペットショップ」「ブリーダー」「里親」という3つの選択肢があります。
この中で、現在の日本で最も一般的な選択肢が、おそらくペットショップから迎える方法でしょう。ペット初心者であれば、それしか方法を知らないという方も少なくないかもしれません。
ここでは、そんなペットを迎える方法それぞれのメリットとデメリットを紹介していきます。
一般的なお迎え方法「ペットショップ」
<メリット>
・気軽に子犬を見に行くことができる
・必要なグッズも一緒に揃えることができる
・いろんな子を実際に抱っこして選べる。
・店員さんから話を聞ける
・気兼ねなく入店できる
・分割無金利払い可能な場合がある
<デメリット>
・仲介手数料が含まれるため、設定されている値段が高め
・血統書が確認できない場合がある
・早期に親犬と分かれていると、社会化が不十分で人や犬に慣れない場合がある
・子犬のブリーダーや両親の確認ができない
アフタフォローが安心な「ブリーダー」


<メリット>
・親犬の確認ができるので、子犬の将来の姿をイメージしやすい
・子犬を一番理解している人の話が聞ける
・生活環境が確認できる
・親の血統書が確認できる
・手数料などが含まれないのでその分価格が低くめ
・お迎え後のアフターフォローが丁寧なことが多く安心できる
・たくさんの犬と一緒に生活しているので、社会化できている場合が多い
<デメリット>
・アクセスが悪い場合が多く気軽に通えない
・支払いは基本的に現金の一括払い
・価格がブリーダーさん次第
・評判や信用は自分で情報を集めて判断するしかない
・極稀に悪質なブリーダーも存在する
「ブリーダーから迎えたい!」という方は、下記「柴犬の子犬を探す」ボタンを押してください。ブリーダーナビで掲載中のかわいい柴犬の子犬をご覧になれますよ!
保護犬の命を救える「里親」という選択


<メリット>
・殺処分される命を救える
・ネット上から最新の情報を得ることができる
・その場の勢いではなく、よく考えてから迎えることができる
・成犬が多く既にしつけができていることも
・生態費用がかからない
<デメリット>
・里親になる条件が厳しく審査に通りづらい
・ワンちゃんによっては人間嫌いなことも
・基本手渡しなので直接赴く必要がある
・中にはケガや病気を抱えた子もいる
子犬をお迎えできるのは生後何日から?
これからワンちゃんを飼おうと考えているペット初心者の方の中には、「子犬は産まれたらすぐに迎えることができる」と思っている人はいませんか?
現在の日本の動物愛護法では、犬や猫の販売は生後50日以降と定められています。
今後子犬の販売は、生後57日からに
2019年6月、犬や猫の販売を「生後56日(8週間)まで原則禁止する」改正動物愛護法が成立し、1~3年以内に施行される予定です。これまでは、「生後49日まで」だったので、1週間遅くなります。
ただし、柴犬を含む日本犬に関しては、これまで通り50日からの販売が可能となっています。
柴犬の子犬を選ぶポイントは?


ワンちゃんをお迎えする方法をを決めたら、いよいよ柴犬の子犬を選んでいきましょう。
柴犬の平均寿命は15歳といわれており、一度家族として迎え入れたら、とても長い付き合いになります。だからこそ、迎える子犬は慎重に選びたいですよね。
では、どんなポイントを見て選べばいいのでしょうか?
ただ漠然と「柴犬を飼いたい!」と考えている人も少なくないでしょう。もちろん、写真を見て選ぶというのも一つの手ですが、それだけでは分からないことも。
そこでここからは、どこを見て子犬を選べばいいのか柴犬選びのポイントをご紹介していきます。
柴犬を選ぶ際はここをチェック!
・手を近づけた時どんな反応をするか
人見知りせず触れられるのが嬉しい子は、積極的に近寄ってきます。一方、手を避けるように後ずさりしたり怯えるような素振りを見せる子は、まだ人に慣れていないのでしょう。
・肉球をチェック
肉球の状態で、ワンちゃんの健康を知ることができます。理想は、つやつやとまっ黒でプニプ二とした弾力がある肉球です。肉球の色は色素の濃さを表し、弾力の強さは足裏がしっかりしている証です。
・頭の形と耳
綺麗な丸みのある頭に、ピンと立った小さな耳がしっかり前を向いているのが理想です。成犬になっても耳が立たないのなら、別の犬種の血が混じっているか、そもそも柴犬ではない可能性があります。また、耳のにおいがきつかったり汚れていたりするようなら、健康面に問題があるかもしれません。
・被毛と皮膚
ツヤがあり、撫でても反発するようなコシがあれば健康な被毛といえるでしょう。毛をかき分けて皮膚の状態もチェックしてください。白ければ問題なし、赤味があるようならアレルギーの可能性が疑われます。また、キズの確認やフケ・脱毛が多くないかも確認しましょう。
・肛門
肛門や便も、子犬の健康状態を確認するために重要なポイントです。肛門が汚れている場合は、下痢など何かしらの体調不良を抱えている可能性があります。ただし、母乳が残っている場合の便は柔らかいことがあるので、混同しないように気を付けましょう。
・抱きかかえた時の感覚
問題は体の大きさではなく重さです。ワンちゃんは被毛があるので、見た目から体重を想像するのは難しいでしょう。健康な子はしっかり筋肉がついているので見た目よりも重たい場合がほとんどです。また、抱えられても怯えることなくいつも通りにしている子は、人に慣れて落ち着いた性格の子といえるでしょう。
・立ち姿
骨格を含めた体のバランスを確認するために、立ち姿も確認しておきましょう。肩、前腕、胸部がしっかりしていて全体的にバランスが良い、力強い立ち姿の子犬が理想的です。骨格的に、真っ直ぐな背骨もポイントといえます。
・目
柴犬の目は、やや三角形で適度に切れ上がり、瞳の色は濃い褐色が良いといわれています。
頭の丸みや耳の付き方、目だけでなく顔全体のバランスと密接に関係しているといわれています。
・口周辺
人間同様、ワンちゃんも乳歯から永久歯に生え変わり、成犬になると上下合わせて歯の本数は42本になります。子犬の頃は、上下6本ずつの切歯と犬歯、は臼歯という構成です。また、健康な歯ぐきはきれいなピンク色で舌の色は濃い方が望ましいといわれているので、この辺りのポイントも確認しておきましょう。
後悔なく子犬を迎えるためには、どんな些細な問題であっても解決して納得した上で決断することが大切です。ブリーダーさんから子犬を迎える場合は、それぞれの特徴や性格などを把握しているので、気になることはいろいろと質問してみましょう。
親犬のここを確認
親犬を確認する場合、母犬がやせているかどうかは、1つのポイントです。
母犬がやせているということは、母乳を通して子犬に栄養を与えているということになります。一見やせ細ってかわいそうに見えるかもしれませんが、それだけ子犬は元気に育っていると見ていいでしょう。
また、ワンちゃんをはじめとした動物は、人間以上に血統が如実に現れます。最も近い血統である親犬を見れば、子犬の将来の姿をある程度予想することはできますが、隔世遺伝のようなケースもあるので、祖先はどんな犬であったか知るためにも、血統書を確認しておくといいでしょう。
オスとメスの違いとは?
柴犬のオスとメスとでは体格に違いがあり、それに伴い運動量にも差が生まれ、メス2、3頭分とオス1頭分が同じくらいの運動量といわれています。
柴犬は元々運動量が多めの犬種なので、やはり散歩の時間は考慮したいところです。
毎日十分な散歩時間が確保できるようならオスの子犬でも問題ないでしょう。しかし、それが難しいようならメスの子犬をおすすめします。ご自身の生活スタイルに合わせて、無理のない飼い方ができる方を選んでください。
また、性格面でもオスとメスでは違いが認められています。
飼い方やしつけ方など、性別によってアプローチの仕方も変えた方がいいでしょう。
下記ページでは、オスとメスの性格の違いも解説しているので、事前にご確認ください。



柴犬の毛色は何種類?
「JKC(ジャパンケネルクラブ)」では、柴犬の毛色を下記の5種類と定めています。
赤、黒褐色、胡麻、黒胡麻、赤胡麻
このうち、全体の8割を赤毛が占めています。
つまり、赤毛以外の柴犬は、滅多にお目にかかることができない珍しい柴犬といえるでしょう。
胡麻毛というのは、赤、黒、白がほどよく混じった色のことで、白や黒以上に珍しい毛色といわれており、この毛色の柴犬を探すのは中々難しいといえます。
一方、ブリーダーナビでは、お客様の検索性を考えて下記の区分に分けて掲載しています。
白色、胡麻色、茶色、赤色、黒色
小さい柴犬「豆柴」はどんなワンちゃん?
柴犬の人気と小型犬の人気を両方取りしたような犬種が豆柴です。
柴犬の日本犬らしいクールさと、小型犬の愛らしさから、とても人気の高い犬種で、多くのファンを獲得しています。
豆柴と柴犬の違いは、基本的に体の大きさだけで、それ以外は柴犬そのもの。性格やしつけ方など、柴犬と同じに考えて問題はありません。
豆柴については下記ページで詳しく解説しているので、興味を持たれた方はぜひご覧ください。



少し気が早い?柴犬の名前はどうしよう


子犬の名前を決めるのは、飼い主としての楽しみの1つではないでしょうか?
「柴犬だから”しーちゃん”にする!」
「茶色いから”チョコ”」
「かっこいい名前がいいから”マックス”にしよう」
これから、決して短くない期間一緒にすごす愛犬の名前だからこそ、考えて悩んで愛情の込もった名前を付けてあげたいですよね。中には、「候補がありすぎて決められない」「悩み過ぎて、どれにすればいいのやら…」と名前決めが難航している方も多いのではないでしょうか?
そんな方のために、「2018年人気の名前ランキング」「柴犬の名前ランキング」「少しユニークな名前」をご紹介します!
もし「どうしても決められない!」というのなら、これらを参考にしてみてはいかがでしょうか。
柴犬にはどんな名前が人気?ランキング紹介
【2018年版 人気の名前ランキング】
☆男の子☆
1位 コタロウ
2位 ソラ
3位 レオ
4位 チョコ
5位 マロン
☆女の子☆
1位 ココ
2位 モモ
3位 ハナ
4位 モカ
5位 モコ
出典:【オスメス犬種別】犬の名前ランキング2018|いぬのきもち
【柴犬の名前ランキング】
柴犬は日本犬なので、やはり日本らしい名前の割合が他の犬種より多くなっています。
☆柴犬の男の子に人気の名前☆
カタカナ表記ですが、漢字で登録された名前もランキング内に集計されています。
1位 コタロウ
2位 コテツ
3位 ソラ
4位 マル
5位 リク
☆柴犬の女の子に人気の名前☆
やはり花の名前や、古風な雰囲気もありながらも、かわいらしい印象のものが人気のようです。
1位 ハナ
2位 サクラ
3位 モモ
4位 アズキ
5位 キナコ
出典:2018年ニューフェイス柴犬に人気な名前ランキング【ジョシーバ&ダンシーバ別】【アニコム調べ】
【少しユニークな名前】
「他の人と名前がかぶりたくない!」
「個性溢れる名前にしたい!」
そんな飼い主さんにオススメの名前を、ご紹介いたします!
・すあま(お餅の和菓子)
・あわゆき(羊羹のような和菓子)
・じゅげむ
・どん兵衛
・わふー(和風)
・ちゃんこ
※ちなみに…
野球界でとても有名なイチロー選手も柴犬を飼っておられるそうで、その柴犬の名前は「一弓(いっきゅう)」。
イチロー選手の名前と、奥さんの名前から1文字ずつ取って名付けたのだとか。
迎えるための心構え


世の中には、犬が大好きという人もいれば、逆に犬が怖い・苦手という人もいます。
「自分が好きだから周りも好きだろう」
と、自分の価値観が当たり前だと思ってしまっては危険です。ワンちゃんの飼い主として、最低限のルールを守って生活することを意識しましょう!また、大切な愛犬を守るため、トラブルを回避するためにも、ルールを守るということは大切です。
ここでは、ワンちゃんをお迎えする前に知っておいてほしいこと、飼い主として守っていただきたいマナーを紹介していきます。
飼い主を対象とした法律で定められた義務
ワンちゃんを飼うということは、飼い主として愛犬の行動に責任を持つことでもあります。
そこで、柴犬を迎え入れる前に、飼い主として知っておくべき3つの義務をご紹介します。どれも、世間への配慮であるとともに愛犬を守ることにもなる、決して無視できないことばかりです。
<犬の登録>
生後91日以上の犬を飼う場合、犬の所有者を明確にするとともに飼育されている場所を把握するため飼い主には30日以内(生後90日未満の場合は、90日を経過した日から30日以内)に市役所へ飼い犬の登録をする義務が課されます。
これにより、万が一狂犬病が発生した場合、迅速な対応をすることが可能です。
引っ越した場合、引っ越し先の市役所で、登録のし直しが求められます。
<年1回の狂犬病予防注射>
狂犬病は、致死率ほぼ100%という恐ろしい病気です。1度発症してしまうと、治療することができないため、予防する以外に対抗する手段がありません。
1957年以降、日本国内で自然発生した狂犬病は確認されていないものの、国外で感染し帰国後死亡した例があります。この事実からも分かるように、狂犬病は決して過去の病気ではありません。
狂犬病の発生を防ぐためにも、必ず年に1回は予防注射を打ってください。
<鑑札と注射済票を飼い犬に装着する>
犬の登録をした際にもらうことができるのが鑑札で、狂犬病予防注射を打ち終わるともらうことができるのが注射済票です。どちらも、上記2つの義務を果たした証明となるので、必ず愛犬に装着させてください。
鑑札には登録番号が記載されているため、愛犬が迷子になったとしても、連絡をもらうことができます。
しかし、どちらもつけていなかった場合、最悪抑留され保健所に連れていかれてしまうので注意しましょう。
参考 犬の鑑札、注射済票について厚生労働省
絶対に守りたい最低限のマナー
法律で定められた義務を守るのは国民として当然ながら、ワンちゃんの飼い主としてそれだけでは十分といえません。愛犬家として、ルールやマナーを守ることが求められます。
もちろん、義務ではないので罰則はありませんが、犬好きとしてコミュニティーの一員として、自分のためにも愛犬のためにもしっかり守っていきましょう!
●最初から最後まで責任を持って
ペットという1つの命を預かる上で、最後まで責任を持ってお世話するのは最低限守らなければいけないルールです。これを守れない人は、ペットをかう資格がないといっても過言ではないでしょう。
どんな理由があるにせよ、捨てたり暴力を振るったりは厳禁!
できる限りの愛情を注いでかわいがってあげてください!
●放し飼いはしないで!
「他人に迷惑をかけないから大丈夫」という勝手な理由で、リードを外したまま散歩をする人がいます。結果的に問題が起こらなかったとしても、これは絶対にNGです!
放し飼いは、周囲を不安にさせる上、場合によっては愛犬にも危険が及びます。
例えば、放し飼いの結果愛犬が「他人にケガを追わせたら…」「いきなり車道に飛び出したら…」飼い主のマナー違反のせいでワンちゃんが犠牲になってしまうのです。
●無計画な繁殖はしない
「子供を産ませたのはいいけれど、引き取り手が見つからない」
「思ったよりたくさん産まれてしまって、育てきれない」
考えもなしに繁殖してしまった結果、こうした事態を招いてしまうと、生まれた子犬の行き着く先は保健所ということになりかねません。そんな悲しい事態を避けるためにも、やはり去勢避妊手術はした方がいいでしょう。
去勢避妊手術に関しては賛否両論あるものの、飼い主としての責任を全うするためにも、必ず考えてほしいことです。
●散歩マナーを守る
飼い主にとって愛犬との散歩は日課です。しかし、そんな毎日の何気ない出来事の中にも、トラブルの芽は隠れています。中でも、最もトラブルの原因となりやすいのは、「うんちの後始末」です。現代においても、散歩の途中で愛犬がうんちをしたにも関わらず、何の処理もせず立ち去る人がいます。これは飼い主として避難されても仕方がない行為といえるでしょう。
ワンちゃんを飼う人間といて、愛犬のうんちは責任を持って処理してください!
●愛犬の健康管理
飼い主である以上、愛犬の健康状態に気を配るのは当然です。狂犬病予防接種は義務ですが、感染症から守るためのワクチン接種もしておくことをおすすめします。それ以外にも、ノミやダニへの対策や、毎日の健康チェックなど、愛犬の健康管理をしましょう。
とはいえ、ケガや病気はどれだけ気を付けていても完全に防げるものではありません。何かあった場合は、すぐに動物病院へ連れていってあげてください。
●動物5つの自由を守りましょう
広く世界的に認知されている「動物5つの自由」をご存知でしょうか。
これは、どんな状況であっても飼っているペットに必ず与えなくてはいけないものとされており、犬に限らず動物に関わるすべての人に知ってもらいたい内容です。
①飢えや渇きからの自由
健康維持のために適切な食事と水を与えること。
②痛み、負傷、病気からの自由
怪我や病気から守り、病気の場合には十分な獣医医療を施すこと。
③恐怖や抑圧からの自由
過度なストレスとなる恐怖や抑圧を与えず、それらから守ること。
動物も痛みや苦痛を感じるという立場から肉体的な負担だけでなく、精神的な負担もできうる限り避けること。
④不快からの自由
温度、湿度、照度など、それぞれの動物にとって快適な環境を用意すること。
身動きもできないせまい場所、糞尿にまみれた状態、日よけのない炎天下、雨や風、騒音などにさらされている、といった飼育環境は動物にとって好ましくありません。
・自由に体の向きを変えることができ、自然に立つことができ、楽に横たわることができる
・清潔で静かで、気持ちよく休んだり、身を隠したりすることができる
・炎天下の日差しや、雨や風をしのぐことができる
⑤自然な行動をする自由
各々の動物種の生態・習性に従った自然な行動が行えるようにすること。
群れで生活する動物は、同種の仲間が必要です。
出典:ペットの「5つの自由」のこと
まとめ


これから柴犬を迎えようと考えている方は、今回の記事を読んで、どんな準備が必要か理解することができたでしょうか?
ワンちゃんを家族に迎えるということは、想像以上に大変で、覚悟が必要な行為です。
それを確認したうえで、柴犬を迎えようと決めた方は、ブリーダーさんからお迎えすることも検討してみてください。
ブリーダーさんはお迎え後のアフタフォローも丁寧で、いつでも相談ができる相手がいるのは心強いですよ。下記の「柴犬の子犬を探す」ボタンからは現在掲載中の柴犬の子犬をご覧いただけます。ぜひ可愛い柴犬の子犬たちをご覧になってみてください。
著者/ブリーダーナビ編集部